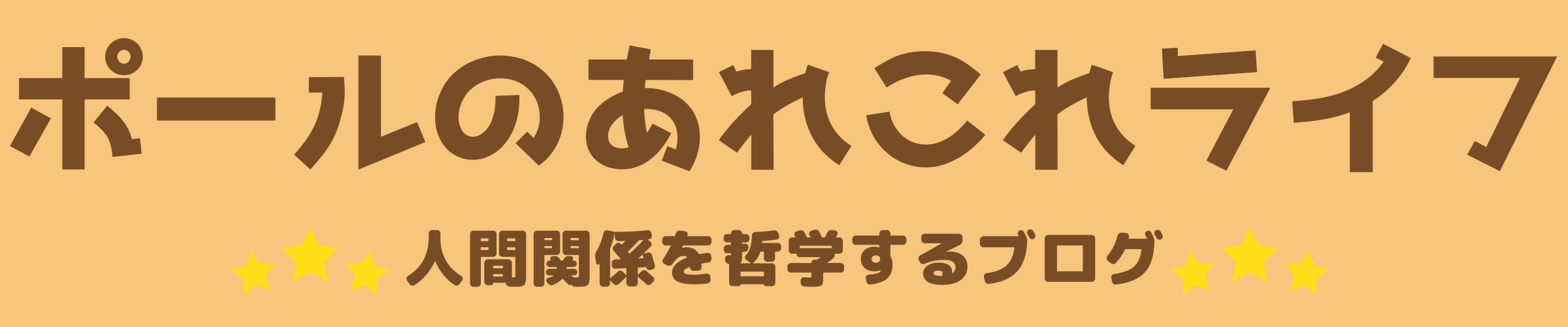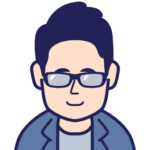過保護な親の特徴を5つと改善方法を独自に解説します【家族円満!】


子どもが大学生になったんだけど、私の行動って子供からしたら過保護かも。どう接していくのが良いのかしら?
こんなお悩みにおススメの記事です。
この記事の解説者

私の親は過保護ではありませんでしたが、小学生の頃は門限のようなものもありました。
子どもが幼ければ過保護になって当然ですが、子どもが中学生になったら勉強以外のことは余計な口を出さない方が良いかもしれません。
- 子どもが大事なので過保護になってしまう
- 過保護が子どもに与える影響が気になる
- 正しく子どもと接する方法を知りたい
私は学生時代に学生から様々な相談を受けてきましたが、意外と子どもが大学生になってもあれこれ口出しする親が多いようでした。
そのような相談に対処してきた経験を活かし、上記のお悩みを解消できれば良い思い、記事を書いております。
ぜひ、最後までご覧いただけると嬉しいです。
過保護な親が子どもの行動力に与える影響

わが子が大切であるがゆえに無意識に過保護になってしまうかもしれませんが、度が過ぎると子どもにとって悪影響があります。
過保護については、一般的には次のことを意味しています。
過保護とは
親が子どもに対して過度な配慮と干渉を与える養育関係の型
コトバンク
過保護の家庭の場合、子どもは親に依存してしまい、積極性が乏しくなるとされています。
自分では何もできないというのは「行動力」が皆無な人間になるということです。
大学を卒業して就職するにも就活という行動が必要ですし、仕事で思い悩んだけど改善して結果を出すことも行動、将来のために投資することも行動です。
このように人生は行動の連続です。
過保護であることが、子どもから「行動力」という最高のスキルを奪ってしまうことになるとしたら、たいへん恐ろしいですよね。
現在、子どもに対して過保護になっているのであれば、子どもが社会に出る前に「行動力」を身につけられるように上手く支援していく親子関係を築く必要があります。
過保護な親の5つの特徴と改善点

ここでは以下のパターンに分け、過保護な親の特徴5つを挙げます。
- 門限が厳しい
- 1日の報告を要求する
- 洋服を選んでくる
- 子どもと学校の仲介役になっている
- 平均以上の金銭的援助を行う
それぞれについて解説していきます。
門限が厳しい
門限については、どこの家庭でも子供が一定の年齢に達するまでは設けていると思います。
門限を何時までに定めるかは各家庭で異なっています。
中学生2年生~3年生になる頃には、徐々に門限を緩めていった方が良いです。
塾で遅くなることについては門限の例外という違和感
上記のように塾通いの場合は帰宅時間が21時を過ぎることがあると思います。
塾で帰宅時間が遅れることには寛容なのに、子供が外に遊びに行く場合は門限を19時とかにしてしまうと子どもにとっては違和感を覚えます。
勉強の時は門限の例外とすると、賢い子どもは上記のようにそれを逆手にとってしまいます。
- 門限は徐々に緩和して、高校生になるころには撤廃
- 子供が出発するときに、帰宅が何時になるか聞いておく
- 帰宅する時間に「これから帰る」程度の簡単なメッセージを送ってもらう
普段から子どもと適切にコミュニケーションできていれば、子ども側も親を心配させまいと考えるので、遅くまで遊ぶようなことはしません。
1日の報告を要求する
たまにであれば問題ありませんが子どもが学校から帰ってきたり、遊びから帰ってきたりするたびに、1日の詳細を聞き出すことは控えた方が良いです。
コミュニケーション目的でその日の出来事などを子どもに聞いたりしているかと思いますが、子どもとしては、親に質問されることについて結構めんどうに思っています。
親からのしつこい質問は子どもにとってはまるで尋問
ちなみに私は反抗期がありませんでしたが、これについては両親が過保護ではなかったことに加え、普段から私に対して質問せず、私をイライラさせなかったことが大きいと思います。
- 子ども自らが1日の出来事を話すまで待つ
- どうしても聞き出したいなら夕食後などのリラックス時間に聞く
子どもとコミュニケーションを取るのであれば、自分から子どもに話をすることを基本としてください。
人は話が弾むと、自ら話をしたくなるようにできているので、質問する以外の方法で子どもに自発的に話をさせた方が良いです。
洋服を選んでくる
子どもがある程度の年齢に達したら、洋服選びは子どもに任せた方が良いです。
基本的に30年以上も昔のデザインセンスで服を選んでいるので確実にダサい
親が勝手に選んでくる場合、基本的には上記のようなダサいものしか選べません。
少なくとも、目を輝かせて洋服を見ていた10代の頃から、30年は経っていると思いますが、若者向けの服を選ぶセンスは当時のままで、ほぼ変わっていないはずです。
子どもの洋服選びについては、以下のことを心掛けた方が良いです。
- 子どもの意見を最優先にし、洋服選びを行う
子どもとしては親が選んだ服に対して、周囲からダサいと言われてしまうと、とても恥ずかしい気持ちになり、反抗期に拍車がかかります。
逆に自分で選んだ服に対して、周囲からダサいと言われれば、次回から服を選ぶときは他のデザインを検討するというように、子どもが自ら考えて改善していくことにも繋がります。
子どもと学校の仲介役になっている
学校とのやり取りについては、小学校~高校までは子どもを通さず、親がやってしまっても良いと思います。
子どもが大学生なのに親が学校と連絡を取り合うのは違和感がある
私は過去、大学におけるアルバイトをしていた際、学生よりも保護者と連絡を取り合う機会が多いことに驚きました。
授業料なら分かりますが、サークルのことや友人関係、奨学金などの学生本人が主体となって連絡すべき内容が多かったっです。
社会人になると自分で物事を考えて行動する機会が増えますし、何も考えていないで仕事だけしていると上司に怒られます。
大学は社会人になるための最後の訓練期間であるのに、親が出てきては子どもの自立が遅くなります。
- 子どもが大学生になったら何事も自分でやらせる
- 余裕があれば一人暮らしをさせる
子どもがある程度の年齢に達したら、基本的な物事は全て自分でやるように教育しましょう。
一人暮らしをすると、身の回りのことを全部やらなければならないので、親のありがたみを痛感できると同時に、1~2年経てば自然と自立できます。
平均以上の金銭的援助を行う
私の大学では同級生にお金持ちがいっぱいいました。
親がお金持ちであっても金銭的援助をあまり受けていない人もいましたが、中にはお小遣いを月に10万円以上もらっている人もいました。
あまりにもお金をもらいすぎると競争心が無くなる
アルバイトをしたとしても、少し大変なことがあるとお小遣いで何とかなるから良いやと考えて辞めてしまいます。
実際、お小遣いを必要以上に多くもらっている友人はアルバイトをするも、どの仕事も長続きしていませんでした。
- お小遣いはどんなに多くとも3万円
- 営業系のアルバイトをさせ、お金を稼ぐことの厳しさを勉強させる
お小遣いについては、多くても3万円程度が良いと思います。
また、子どもの向上心を高めるために、営業系のアルバイトをさせることがおススメです。
私の実体験になりますが、私の性格は元々は楽観的でポカ~ンとしており、他人と競おうとする精神が足りない人間でしたが、以下のようなアルバイトを経験しました。
上記を経験したことで、学生のうちに社会でお金を稼ぐことの厳しさを痛感しました。
お金を稼ぐ厳しさを知ったと同時に自ら考え、商品やサービスを売る楽しさを味わうことができました。
営業系アルバイトを見つけて紹介するといった子どものためになることであれば、干渉して良いと思います。
過保護な親にならず子どもと良い関係性を築く方法

子どもの話をじっくり聞いてあげられる親になり、子どもの心の支えになってあげることが強固な信頼関係を築くために重要です。
口で言うのは簡単ですが、困った人にアドバイスをすることは、例え我が子であっても難しいですよね。
- 朝食を一緒に食べる
- 夕食を一緒に食べる
- 一緒の趣味を見つける
- リビングで一緒にくつろぐ
重要な点は一緒に穏やかな時間を過ごすことです。
1日に1回は子どもとリラックスして同じ空間に居られる時間を作りましょう。
子どもが困ったような表情をした時は遠慮なく「何かあった?」と聞いてください。
悩んでいる時に声をかけてもらえる
上記の関係性で干渉しすぎないように子どもに接していけば、大人になっても良好な親子関係でいられるはずです。
過保護な親の特徴と改善方法のまとめ

今回は過保護な親の特徴5つと改善策をまとめました。
- 門限が厳しい
- 1日の報告を要求する
- 洋服を選んでくる
- 子どもと学校の仲介役になっている
- 平均以上の金銭的援助を行う
上記のようについつい子どもに過保護になってしまう場合は、以下の点に留意しつつ改善していくことで子供と良好な関係を築けます。
- 門限は徐々に緩和し、ある程度の年齢には撤廃
- 子どもに1日の報告を求めず、子どもから話をしてくれるのを待つ
- 洋服は勝手に選ばず、子どもの意見を尊重
- 子どもが大学生になったら身の回りのことを自分でやらせる
- 過度な金銭的支援を行わず、多少アルバイトが必要になる程度のお小遣いに留める
- 一緒にリラクックスして話せる時間をつくる
これらの改善を図ることで、子どもを早期に自立さ、物事を自分の頭で考え行動するための基礎を作れます。
子どもを教育しつつ、円満な家庭を築き、人生(ライフ)をより豊かにしていきましょう。